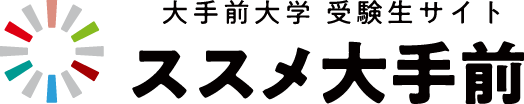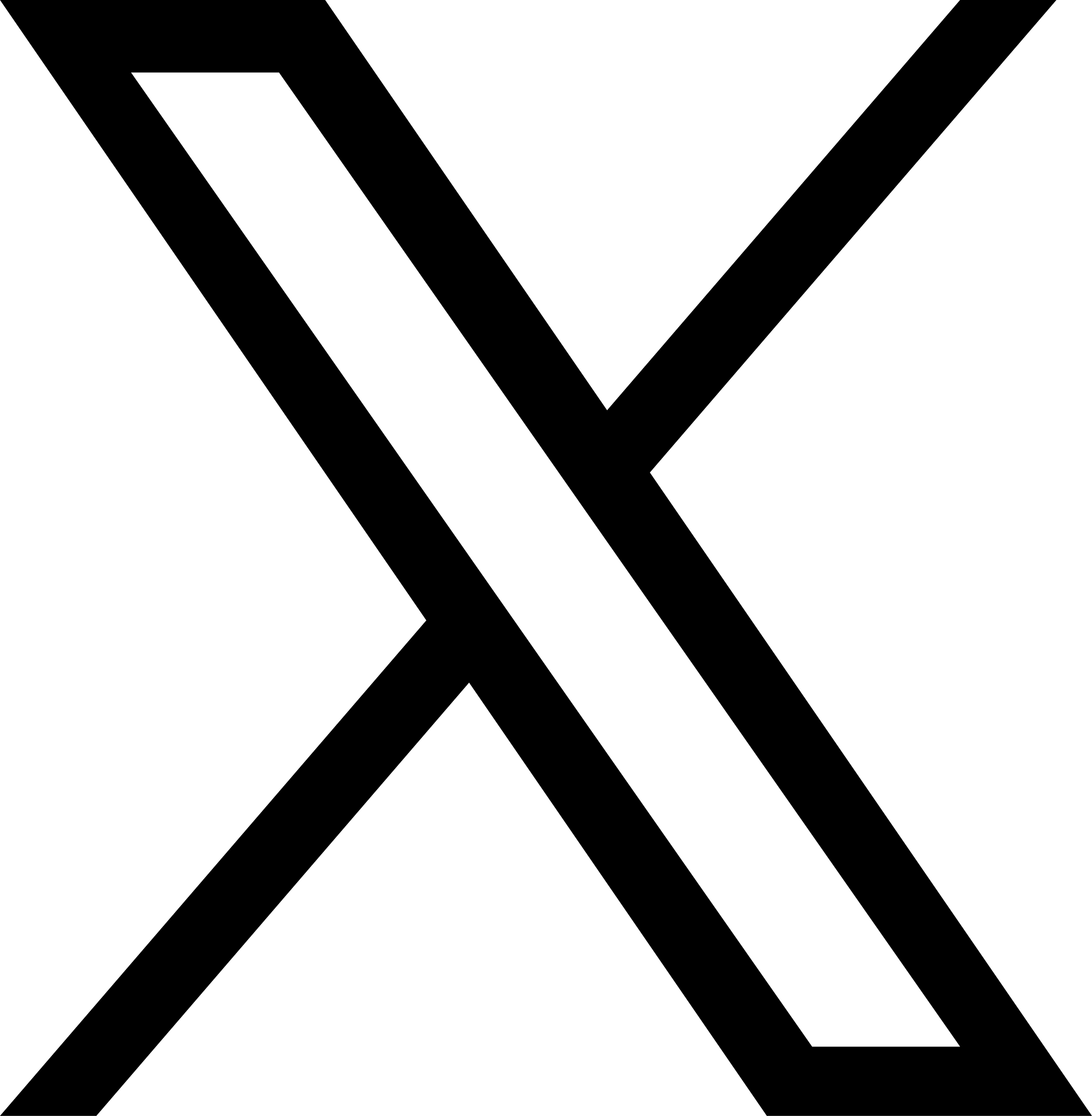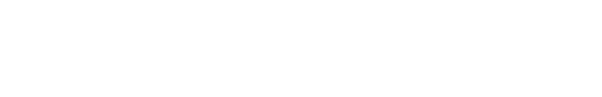TOPICS
学部紹介
MORENEWS 最新情報
MORE-
2024.04.18 ニュース
【国際看護学研究科】保健師・助産師交流カフェを開催しました
-
2024.02.22 ニュース
【国際看護学部】大谷高校主催の「ミライノトビラ」に参加しました
-
2024.02.08 オープンキャンパス
【高校生の皆さま】2024年度「オープンキャンパス」申込受付開始!
-
2024.01.31 入試
能登半島地震により被災された受験生ならびに入学予定の皆さま
-
2024.01.22 入試
1月24日・25日 入学試験に参加されるみなさまへ
-
2024.01.16 イベント
【受験生の皆さま】2/3(土)大手前プレゼンフェスタを開催いたします
-
2023.12.25 入試
大学入学共通テスト 大手前大学 さくら夙川キャンパス会場で受験されるみなさまへ
-
2023.11.22 ニュース
【公立学校教員採用試験】2023年度 2名の学生が合格!
大手前大学が
選ばれる理由
MORE