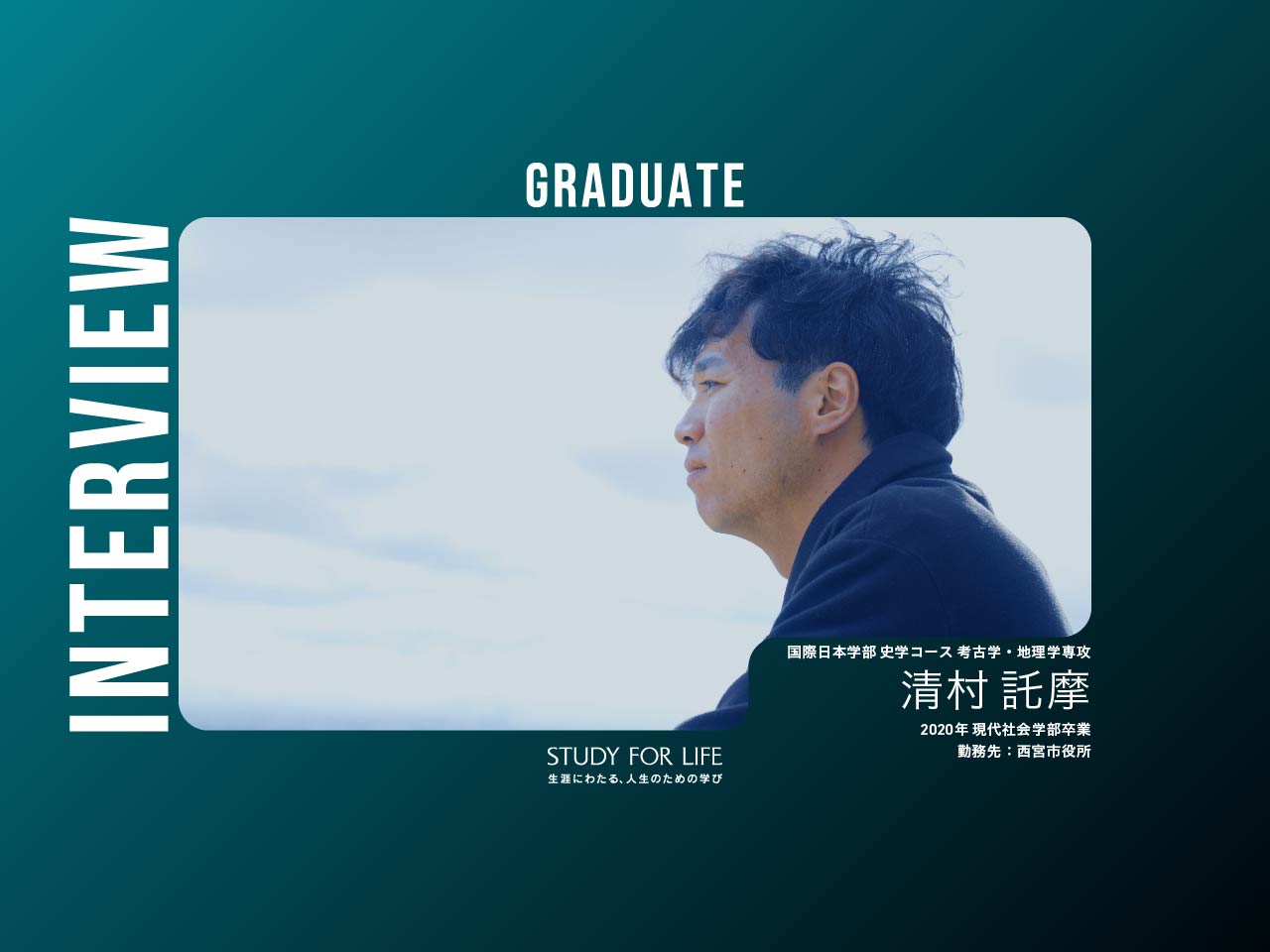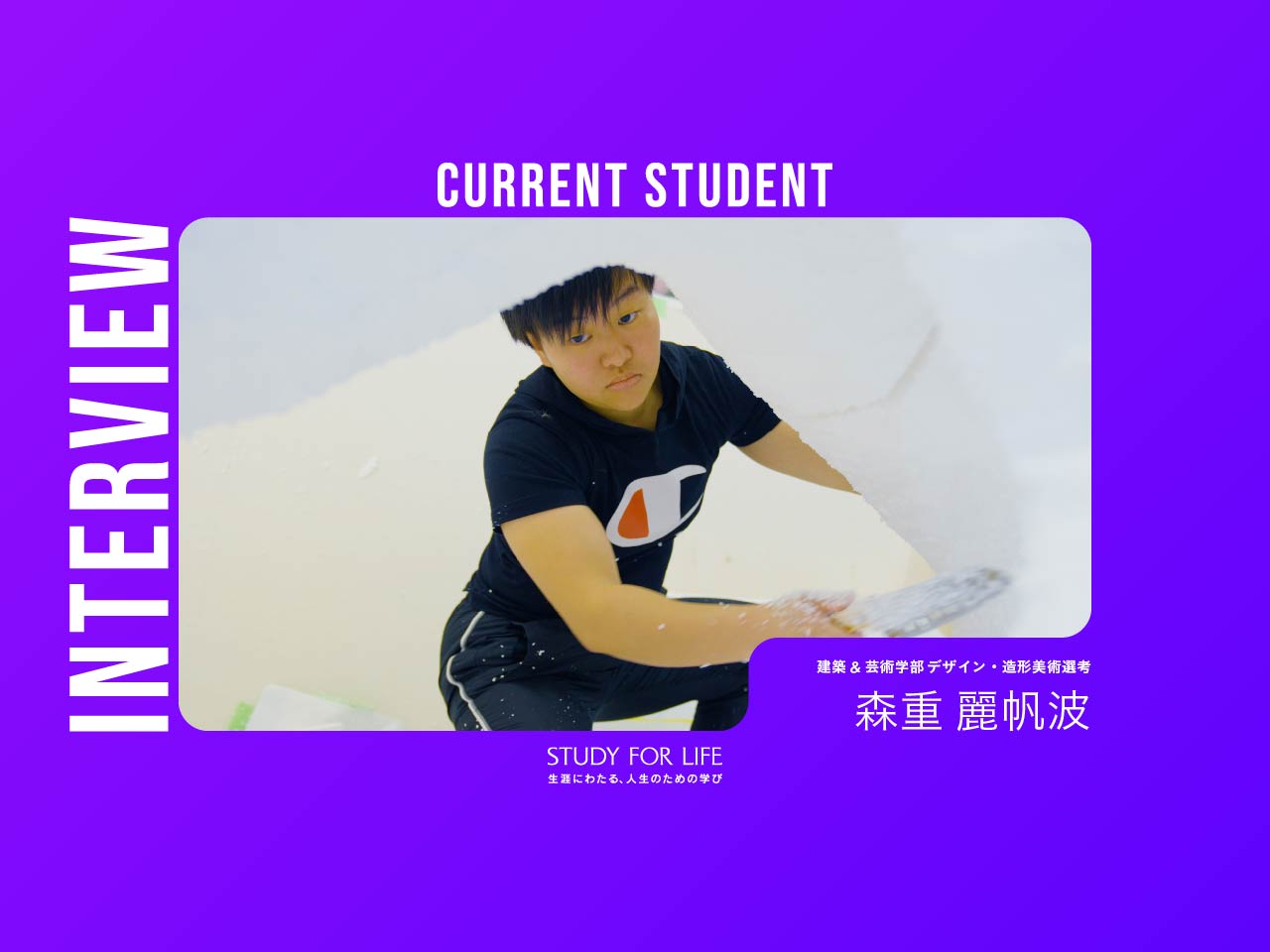わたしたちの「ゆさぶる ささる 胸を打つ」
先生方の手厚いサポートと熱い想いが、今の私を支えている

社会医療法人頌徳会 日野病院 管理栄養士
天野 桃花さん
大学に入学して具現化できた、私の「夢」
もともと食べることが好きで「栄養」に携わる仕事に興味を持ったことが、管理栄養士をめざしたきっかけです。大手前大学は各クラスの人数が少ないことや、私の入学時に健康栄養学部が四年制大学として新設されたばかりだったことから、就職のサポートが充実していそうだと感じ、入学を決めました。入学後は、国家試験に向けた勉強の傍ら、食品メーカーの工場見学や地域の食に関するイベントに参加する「ベンチャー部」の部長として活動していました。食品の生まれる過程や、工場の衛生管理について学べる機会は今から考えても貴重な経験で、現在の仕事にも活きています。また部長として部員に頼られる機会も多く、この経験を通して「リーダーシップ」が自分の強みだと気付けたことも、私の人生において大きな出来事です。
担任の先生との「1on1」もまた、私の背中を押してくれました。先生は入学当初に「自分のしたいことを仕事にする人がいれば、自分に合った仕事をする人もいる。色んな人がいるから、仕事に関する自分の軸を学生のうちに発見できたほうがいい」という言葉を、私たちに掛けてくださりました。学生時代からスポーツを続けていたことから、入学時はアスリートの栄養を管理する「スポーツ栄養」に興味がありました。しかし、介護施設や病院での実習を通して「健康な方をサポートするよりも、まずは病気の方に寄り添うための知識を身に着けたい」と気付きました。「1on1」で先生にその思いを伝えたときも賛同してくださったので、自信を持って進むべき道を決めることができました。

今も心に残っている、先生方がぶつけてくれた合格への想い
大学生活で心を揺さぶられ、胸を打たれたのは「国家試験に絶対に合格させてあげたい」という先生方の強い思いです。在学時代は、どの先生からもこの強い想いを感じました。正直に言うと、長い大学生活の中で、時には勉強に身が入らない時期もありました。しかし先生方が、国家試験のために絶対に押さえておくべきポイントを常に伝えてくださったおかげで、メリハリのある4年間を過ごせたように思います。授業中も先生の講義を一方的に聞くのではなく、その場で気軽に質問できるような雰囲気を作っていただき、学生とのコミュニケーションを大切にしてくださいました。また、大手前大学には「国家試験対策サポート室」があり、試験を熟知した先生方がいつでも質問に答えてくれます。どうしても覚えられない内容があれば、暗記のこつを教えてくれ、意味が理解できるまで指導いただくなど、手厚いサポートを受けられました。病院での勤務を希望していた私は、病気に対する食事療法を学ぶ「臨床栄養」の勉強に力を入れていましたが、覚えることが多いので大変苦戦しました。しかし、先生がオリジナル教材を準備してくださり、試験前には「この資料のみを覚えればいい」という状態にしていただいたので、無事に試験を突破することができました。

就職先を探すにおいて「キャリアサポートセンター」も活用しました。どの病院で働くかを決めるにあたって、まずは「救急医療病院」か「回復期病院」のどちらを選択するかを絞るために相談。説明会の案内や見学方法を教えていただいたことにより、今の勤務先に出会うことができました。各分野によって面接や小論文の対策方法もまったく違うため、その都度アドバイスをいただくことで、自信を持って就職活動に臨めました。先生方のあの熱意には、今でも感謝しています。

管理栄養士として、親しみやすさを大切にしたい
大学卒業後は介護老人保健施設や特別養護老人ホームでの業務を経て、3年目からは現在の病院で管理栄養士として従事しています。私が入職した頌徳会グループは回復期医療や透析医療に加え、介護老人保健施設や特別養護老人ホームなど、高齢者に必要な医療と介護を提供しているグループです。2040年頃には高齢者数がピークになることを踏まえ、回復期リハビリテーション病棟には管理栄養士の病棟配置を求められるなど、当院は管理栄養士にとって益々働きがいのある病院になっています。そんな中で、現在は主に病棟に常駐して栄養管理を行っています。入院患者さんの食生活を聞き取り、退院後の食生活の見直しや低栄養予防のために栄養指導を行います。また嚥下面では退院後も同じ食生活ができるように医師、看護師やリハスタッフと協働して、嚥下訓練を補助することもあります。塩分や糖質の管理はもちろんですが、まずは患者さんに食べてもらえるようなおいしい病院食を意識しています。

大学で受講した「栄養教育論」で、相手の栄養への関心度によって、伝え方を工夫する方法を学べる授業がありました。まさにその知識が現職で役立っています。いきなり患者に「この栄養が何グラム必要です」と言っても、イメージが湧く方のほうが少ないでしょう。そういうときは「お肉3枚分くらいを増やしましょう」や「スーパーのお惣菜ではこんなものを選びましょう」とイメージのつきやすい表現で伝えてみたり…それでも無関心な方には、まずは心を開いてもらおうと、まったく関係のない話から始めるようにしています。これらは先生方が私たちに実践してくださった説明方法でもあります。
大学の先生方は、学生からも話しかけやすいようにコミュニケーションを取ってくださりましたが、今は私が患者さんと接する立場になりましたので、いつでも話かけやすい、頼れる管理栄養士でいたいと思っています。中には、生活習慣病にかかってしまったことで諦めてしまう方もいるのですが、できる限り栄養に興味を持ってもらえるように働きかけ、どんな人でも食を我慢しなくていいようにサポートすることが、私の役目だと自負しています。
管理栄養士は活躍の場が多岐に渡るからこそ、どのフィールドで自分の力を生かしたいか悩む方も多いでしょう。私もその一人でしたが、支援が手厚い大手前大学に進学したことで、とことん寄り添ってくださる先生方に出会え、向かいたい未来を見つけることができたのだと思います。

※内容はすべて取材時のものです。(2025年3月)