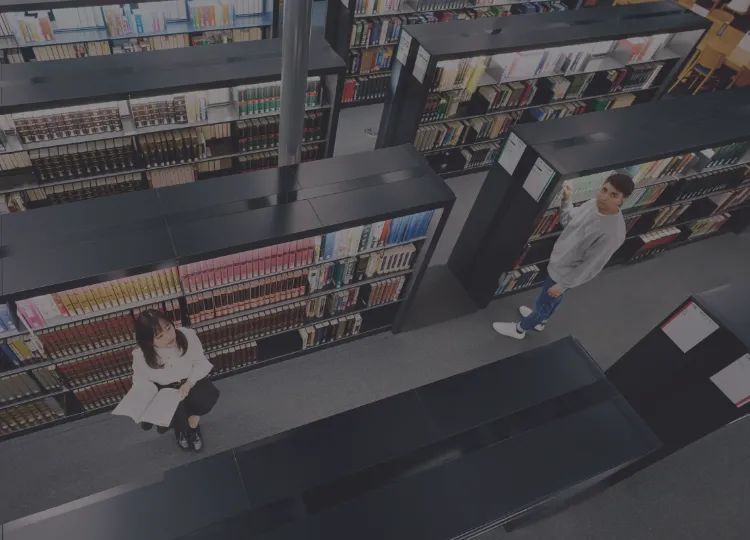
教学運営の基本方針
比較文化研究科比較文化専攻(博士前期課程)(修士課程)
3つのポリシー
ディプロマ・ポリシー
(修了認定・学位授与の方針)
- 大手前大学大学院比較文化研究科博士前期課程においては、同課程所定の科目を30単位以上修得し、かつ必要な研究指導を受け、学位論文の審査に合格することにより、次項に示すような能力を身につけた者と認め、修了を認定し、修士の学位を授与する。
-
本学の大学院生が博士前期課程を修了するにあたって、身につけるべき能力
- (ア) それぞれの専門を深く理解し、体系的にそれを表現できる知識と能力をもつこと。
-
修士論文審査基準
- (ア) 研究テーマの明確さ:研究テーマの問題設定が明確であること。
- (イ) 先行研究に関する十分な知見:上記(ア)の問題設定に関して、先行研究についての十分な知見を有し、研究史上の自らの問題設定の位置づけが明確であること。
- (ウ) 情報収集の深度および適切さ:上記(ア)の問題設定にもとづいて、文献やデータを十分に収集し、かつ適切に利用すること。
- (エ) 論文作成能力:学位論文としての形式を備えていること。また、確かな文章表現によって論文作成がなされていること。
- (オ) 論旨の一貫性および明確さ:論文全体の構成が一貫した、また明晰かつ客観的妥当性のある論理に基づいて立論されていること。
- (カ) 先行研究に対するオリジナル性:結論として独自の学問的知見を備えていること。
- (キ) 研究倫理への配慮:研究倫理への十分な配慮がなされていること。
カリキュラム・ポリシー
(教育課程編成・実施の方針)
日本をはじめ世界各地域の文学、歴史、思想、社会、芸術などの文化現象の比較研究を行うとともに、国際社会に対応しうる高度な専門知識と広い視野を備えた人材を育成する。この方針に基づいて、修士論文作成に導く必修科目、基礎科目及び関連科目を設置し、専門分野と関連分野の学習、研究を互いに有機的に連携し、補強する教育課程を編成し、実施する。
アドミッション・ポリシー
(入学者受入れの方針)
本学の建学の精神である「STUDY FOR LIFE」に則り、日本をはじめ、欧米、アジア諸国における文学、歴史、思想、社会、芸術など文化現象の比較論的研究・調査を行うとともに、調和のとれた国際感覚を有し、とみにグローバル化へと進む世界への貢献を可能とする優れた資質を備えた学生を受け入れる。
比較文化研究科比較文化専攻(博士後期課程) 3つのポリシー
ディプロマ・ポリシー
(修了認定・学位授与の方針)
- 大手前大学大学院比較文化研究科博士後期課程においては、必要な研究指導を受け、学位論文の審査に合格することにより、次項に示すような能力を身につけた者と認め、修了を認定し、博士の学位を授与する。
-
本学の大学院生が博士後期課程を修了するにあたって、身につけるべき能力。
- (ア) 自身の専門分野において、深い思考力と広範な知識を身につけ、自立した研究者としての能力を修得していること。
-
博士論文審査基準
- (ア) 研究テーマの明確さ:研究テーマの問題設定が明確であること。
- (イ) 先行研究に関する十分な知見:上記(ア)の問題設定に関して、先行研究についての十分な知見を有し、研究史上の自らの問題設定の位置づけが明確であること。
- (ウ) 情報収集の深度および適切さ:上記(ア)の問題設定にもとづいて、文献やデータを十分に収集し、かつ適切に利用すること。
- (エ) 論文作成能力:学位論文としての形式を備えていること。また、確かな文章表現によって論文作成がなされていること。
- (オ) 論旨の一貫性および明確さ:問題設定に基づく仮説を検証するために、論文全体の構成が一貫した、また明晰かつ客観的妥当性のある論理に基づいて立論されていること。
- (カ) 先行研究に対するオリジナル性:結論として独自の学問的知見を備えていること。そしてその成果の一部が、全国レベルの学会誌の投稿に耐えうるものであること。
- (キ) 研究倫理への配慮:研究倫理への十分な配慮がなされていること。
-
博士論文審査体制および審査手続き
- (ア) 博士論文を提出する者は、提出前年度の「博士学位論文構想中間報告会」において研究テーマ、論文の構想等について発表しなければならない。また、博士後期課程において勉学した成果を証するものとして、その成果が論文または研究ノートとして、学会誌または大学の紀要などで公表されていること。
- (イ) 課程博士学位論文作成能力を問うために、博士学位論文予備審査を行う。審査は、研究科委員会の定める予備審査委員会によって行われる。予備審査委員会は主査(研究指導教員)、副査2名以上をもって構成される。予備審査は、公開にて行われ、学生による論文の概要説明の後,主査・副査により質疑応答が行われる。これにより、博士論文提出の可否が審査され、研究科委員会において判定が決められる。
- (ウ) 学位申請者が提出した博士論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員会によって行われる。審査委員会は主査(研究指導教員)1名、副査2名以上をもって構成され、上記第3項の審査基準に基づき、当該論文を査読の上、審査ならびに口頭試問(必要に応じ筆答)による最終試験をおこなう。論文審査ならびに最終試験の結果により成績審査をおこない、比較文化研究科委員会において学位授与の可否を決定する。
カリキュラム・ポリシー
(教育課程編成・実施の方針)
日本をはじめ世界各地域の文学、歴史、思想、社会、芸術などの文化現象の比較研究を行うとともに、国際社会に対応できる高度な専門知識と広い視野を備えた人材を育成する。この方針に基づき、各自の博士論文作成に導く研究指導のほか、前期課程のいずれの授業科目をも履修できることを前提とした、自己の研究の基盤をさらに広く深く掘り下げるための教育課程を編成する。
アドミッション・ポリシー
(入学者受入れの方針)
本学の建学の精神である「STUDY FOR LIFE」に則り、日本、欧米、アジア諸国を中心として、世界各地の文学、歴史、思想、社会、芸術など文化現象の比較論的研究・調査を行うとともに、高度な専門知識、調和のとれた国際感覚、さらにとみにグローバル化へと進む世界への貢献を可能とする優れた資質を備え、既にその研究実績に基づいて独自の研究テーマを確立し、さらにそれを深く研究しようとする意欲を有する学生を受け入れる。
国際看護学研究科看護学専攻(修士課程)3つのポリシー
ディプロマ・ポリシー
(修了認定・学位授与の方針)
国際看護学研究科看護学専攻では、以下の3つの基準に達している者に修士(看護学)の学位を授与する。
- グローバル社会における看護実践の基盤となる保健・医療・看護や健康支援の多様性を理解し、看護や医療に関する幅広い知識と倫理観を持って対象の価値観を尊重する国際性を修得している。
- 看護実践の場に内在する多様な健康課題を科学的分析力や論理的思考力によって探求し、グローバルな視点によって様々な健康課題の改善に取り組むための基礎的研究力を修得している。
- グローバル社会に内在する健康課題の解決に向けて、専門分野の知識・技術の理解と研究を通して、専門性と独創性のある看護実践力を修得している。
カリキュラム・ポリシー
(教育課程編成・実施の方針)
国際看護学研究科看護学専攻では、ディプロマ・ポリシーに掲げる目標を達成するため、共通科目、専門科目、特別研究科目を体系的に編成し、講義、演習、実習を適切に組み合わせた授業科目を開講する。また、コースツリーを用いて教育課程の体系性や構造を明示する。教育課程編成、教育内容、教育方法、学習成果の評価については、以下のように方針を定める。
- グローバル社会における看護実践の基盤となる保健・医療・看護や健康支援の多様性への理解を深め、対象の特性や価値観を尊重する国際性を涵養するために、「共通科目」に国際看護の基礎を学修する「研究基盤科目」と新しい視座を持つための「研究関連科目」を配置する。
- 看護実践の場に内在する多様な健康課題を科学的分析力や論理的思考力をもって解決する看護を探求する研究力を涵養するために、国際看護学の研究力の基礎を学修する「研究基盤科目」と、研究の新しい視点を学修する「研究関連科目群」を「共通科目」に配置し、修士論文を作成する「特別研究科目」を配置する。
- グローバル社会に内在する健康課題の解決に向けて、専門性かつ独創性のある看護を実践する能力を涵養するために、『看護実践科学分野』・『公衆衛生看護実践科学分野』・『助産実践科学分野』の各分野に「専門科目」を配置する。
- 学習成果の評価基準は、シラバスに明示し、講義では、試験およびレポート課題を中心に評価を行い、演習では、事前自己学習、演習への参加態度、プレゼンテーションなどで評価を行う。
アドミッション・ポリシー
(入学者受入れの方針)
国際看護学研究科看護学専攻のアドミッション・ポリシーを以下のように定める。
- 教育・研究目的
国際看護学研究科看護学専攻では、『看護実践科学分野』『公衆衛生看護実践科学分野』『助産実践科学分野』の3つの分野を基軸に、グローバル社会に暮らす個人・集団・地域がもつ多様性を包括的にとらえ、事象の分析力や客観性を培い、科学的思考をもって課題解決に取り組み、対象のニードに沿った看護を探求する看護職、および時代によって変容する社会に対応できる公衆衛生看護学や助産学の知識・技術を有した保健師および助産師を養成することを目的とする。 - 人材養成の指針
国際看護学研究科看護学専攻では、グローバル社会に暮らす個人・集団・地域が有する多様な特性を理解・尊重し、そこに暮らす人々が、QOL(クオリティオブライフ)を維持しながら豊かで安寧な生活が送れるように、看護の理論と実践に基づいた課題解決能力を培い、対象のニードに沿った看護を探求し、人々の健康と看護学の発展に寄与する人材を養成する。また、時代や環境の変化に沿って変容する人々の健康課題について、主体的に多職種と連携・協働しながら、看護の専門性と科学の理論的思考をもって課題解決に取り組み、国内外における看護実践や教育・研究活動を継続させながら自己研鑽ができる人材の養成を目指す。 -
アドミッション・ポリシー
国際看護学研究科看護学専攻では、上記の目的を達成するために、以下のような人物を求める。- (1) 看護師免許取得者(見込みを含む)で、看護師としての基本的な知識や技術を有し、研究科での学修や研究のために必要な基礎的英語能力を有する者。
- (2) グローバル社会に内在する多様な健康課題に高い関心を持ち、研究的視点によって看護を探求し、看護実践の向上に取り組む意欲のある者。
- (3) 看護実践に根差した研究能力を修得し、広く俯瞰的に物事を捉え、将来にわたって看護を探求する意欲のある者。
- (4) 看護職としての経験を通して、グローバル社会に対応した専門性のある看護実践能力の修得に意欲のある者。
- (5) グローバル社会に暮らす多様な人々への健康支援に強い関心を持ち、包摂社会の形成に向けて取り組む公衆衛生看護実践科学を学ぼうとする者。
- (6) グローバル社会に暮らす多様な女性や子どもの健康支援に加えて、国内外の母子保健の向上に強い関心を持ち、対象のニードに寄り添った助産実践科学を学ぼうとする者。
