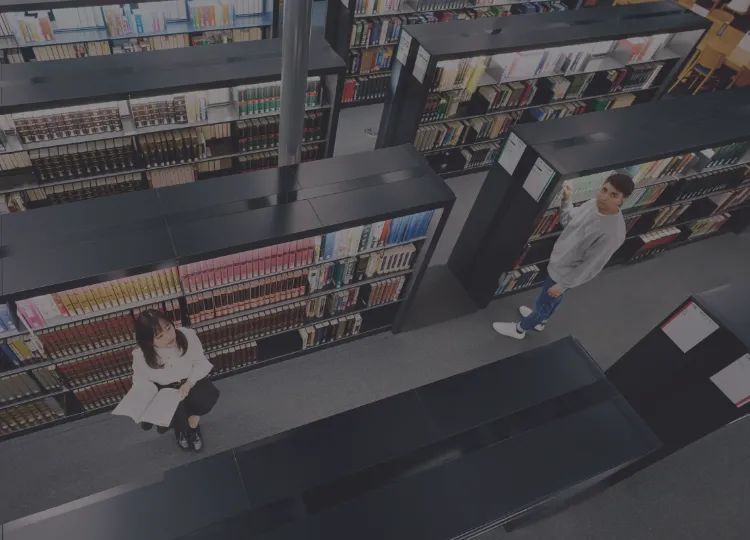
教学運営の基本方針
通学課程全体 3つのポリシー
ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)
大手前大学は、本学の建学の精神、目的、使命および教学運営の基本方針に基づき、社会に貢献できる価値ある人材として認める学生に対して卒業を認定し、学位を授与します。所定の期間在学し、使命および教学運営の基本方針に基づいて設定された授業科目を履修して、基準となる単位数、専攻プログラム、必修プログラム等を、定められた成績評価基準を満たして修めることが学位授与の基準となります。
本学は、学生の学修成果を可視化し、厳格かつ公正な評価基準に基づく成績評価を行うことにより、学位授与者が建学の精神である“STUDY FOR LIFE(生涯にわたる、人生のための学び)”を実現するのに必要な以下の知識、実践力、信念と志を有していることを保証します。
- 豊かな教養と専門知識およびその活用力を有している。
- 優れた国際感覚と他者と協働して問題を解決する能力を有している。
- 豊かな人間性と肯定的自己概念および社会的責任を果たそうとする強い意志を有している。
カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)
大手前大学は、本学のディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)が定める知識、実践力、信念と志を有し、社会に貢献できる価値ある人材を育成すべく、以下の方針に基づきカリキュラムを構築します。
-
本学の教育課程は、リベラルアーツ教育を重視しながら編成されます。
各学部における専門教育を柱としつつ、さらに学生は主体的に専門分野の垣根を越えた幅広い知識や問題解決力を身に付けます。学修の成果を上げるために、カリキュラムは学術の系統性や学修の順次性に配慮して編成されます。
初年次教育やキャリア教育も本学のリベラルアーツ教育を構成します。入学から卒業までの教育課程を通じて、学生は地域あるいは国際社会の多様性を知り、変化や困難に柔軟に対応する能力を身に付けていきます。 -
ディプロマ・ポリシーにあるように、本学の教育は、幅広い知識を身に付け、これを活かして他者とともに問題の解決にあたる力を養成し、さらには学修の内容や活動の振り返り(リフレクション)により、豊かな人間性と肯定的自己概念および社会的責任を育むことを目的としています。カリキュラムにおいては、他者とともに課題解決のプロジェクトを通して学ぶPBLを取り入れ、さらに専門分野の垣根を越えて広く豊かな学術の知見を用いて解決策を考えるクロスオーバーの学びと、教室を飛び出し実際の社会(フィールド)に出向いて実践的な探究活動をおこなう越境(クロスバウンダリー)の学びを重視します。
知識を得て、実践し、その経験の振り返りをおこない、また新たな知識を求める。このようなサイクルを繰り返して学生が能動的に自らを高めていくのが本学リベラルアーツ教育の学修方法の柱となります。
そこで、このような教育を実現するために、本学の各授業科目は、下記の項目(ディプロマ・ポイント)を一つ以上含んで構成されるものとします。ディプロマ・ポイント:
① Knowing(知識とリテラシー)- 教養と専門知識
- 知識・情報を活用する力
② Doing(実践力)
- 国際感覚
- 協働的問題解決力
(1)対人基礎力
(2)対自己基礎力
(3)対課題基礎力③ Being(信念と志)
- 豊かな人間性と肯定的自己概念
- 社会的責任
- 以上の学修の成果は、まず成績をもって評価されます。成績評価は、その基準がシラバスによって明示され、厳正かつ公正におこなわれます。また、成績と同時に外部アセスメントや定性的評価の手法をも加味して多角的に評価がなされ、可視化がおこなわれます。
- 本学の教育課程は、地元自治体や企業、他学の教員等から編成される外部評価委員の意見、また学生からのアンケート調査の内容をも踏まえて、不断の点検と改革がおこなわれます。これにより、常に教育の質が保証されます。
ディプロマ・ポイントについて
ディプロマ・ポイントを学部毎の3つのポリシー内で記載する場合は、以下のとおりとします。
- 個々のディプロマ・ポイントを示す場合
ディプロマ・ポイント①の1.を示す場合 … DP①1 と表記
ディプロマ・ポイント③の2.を示す場合 … DP③2 と表記 - 複数のディプロマ・ポイントを示す場合
DP①1とDP①2を示す場合 … DP① と表記
DP①とDP②2を示す場合 … DP①、DP②2 と表記
アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)
大手前大学は、本学の建学の精神、目的、使命および教学運営の基本方針に共感し、知識、実践力、信念と志を育み、社会に貢献できる価値ある人になろうとする意欲と能力に富んだ学生を求めています。また、さまざまな適性と多様な背景を持った学生を国内外から幅広く受け入れます。
そのために、基礎となる学力の3要素である①知識・技能、②思考力・判断力・表現力等の能力、③主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度を多面的・総合的に評価するための多種の選抜方式を用意し、公正かつ厳正な選考を行います。
具体的には、本学は以下のような素養と意欲を備えた人材を高く評価します。
- 豊かな教養と専門知識およびその活用力を修得するために必要な基礎的知識・能力
- 優れた国際感覚と他者と協働して問題を解決する能力を身に付けようとする意欲
- 豊かな人間性と肯定的自己概念を獲得し、社会的責任を果たそうとする意志
各学部 3つのポリシー
国際日本学部 3つのポリシー
ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)
大手前大学国際日本学部は、所定の卒業要件を満たし、以下の目標に到達した学生に対して卒業を認定し、学士(学術)を授与します。
通学課程全体のディプロマ・ポリシーは、知識、実践力、信念と志を有し、社会に貢献できる価値ある人材を育成することを定めています。このことを基礎として、国際日本学部は、従来の人文系学部とは異なる国際的視点にもとづく歴史、言語、文化、文学の素養を持ち、俯瞰的、総合的なビジョンの形成に資する人材を育成するという具体的な目標を設置しています。一方では、日本の歴史、言語、文化、文学を学びこれを世界に向けて発信できる人材を、また他方では、世界の歴史や言語、そして文化や文学の素養を身につけ、グローバルな視点から日本社会のあり方を再構築することに資する人材を、それぞれ育むことを目標とします。
このような人材育成の目標から、国際日本学部を卒業するには、以下の要件が求められます。
- なによりも歴史、言語、文化、文学について豊かな教養と専門知識、およびその活用力を有していること。
- 専門知識や活用力をもつというだけでは、俯瞰的、総合的なビジョンの形成に資する人材とはいえない。単純に知識を学んで終わるのではなく、これをフィールドワークをはじめとするさまざまな体験をつうじて現実の諸問題(国際協力や国内外においても必要な多様な文化の共生、地域のまちづくり、文化財保存や歴史認識の問題等々)に対処する優れた国際感覚、そして他者と協働して問題を解決する実践力を有していること。
- 現実の諸問題に実践的に向き合い、振り返りを繰り返すことで、上記二つの能力を、さらに豊かな人間性と肯定的自己概念、および社会的責任を果たそうとする強い意志を有するまでに昇華していること。
以上の三つの能力を身につけることが、本学部の人材育成の目標に到達する要件です。
カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)
国際日本学部は、ディプロマ・ポリシーにおいて国際的視点にもとづく歴史、言語、文化、文学の素養を持ち、俯瞰的、総合的なビジョンの形成に資する人材を育成することを学部固有の目標と定めました。本学部は、これを通学課程全体のカリキュラム・ポリシーに謳われた学部の専門教育を柱としつつ、さらにクロスオーバーによる幅広い知識修得、クロスバウンダリーな実践的探究活動、そして常なるリフレクションといった学修方法をつうじて実現していきます。
- 1、2年次では基礎的な情報機器の活用、文献検索や資料講読、問題提起、解題の方法、発表をつうじてレポートの書き方などを学んでいきます。このときに、クロスオーバーによる履修をおこなうことで将来的に自分の専門を決める際に役立つ幅広い知識が得られます。
-
3、4年次ではより深く専門科目を学修する一方で、各コースに分かれた少人数の専門演習が始まり、将来の自分自身の進路を見据え、プレゼンテーションや卒業研究に向けて取り組みます。
各コース、そしてそれを構成する各専攻のカリキュラムは以下の方針のもとに編成されています。[史学コース]
歴史を学ぶことの意味は、過去の研究をつうじて現在のあり方を確かめ、未来への手がかりを得ることにあります。本学の史学コースは日本史、東洋史・西洋史、考古学・地理学の各専攻から構成されますが、各分野を幅広く修得し、一国史的な発想にとどまらないグローバルな歴史認識や文化財の保存・研究・活用に関する意識を持ち、豊かな人間性と今日の社会に責任を果たそうとする強い意志を身につけることを目標とします(DP②1、DP③)。
この目標に向けて、史学コース各専攻では、概説的講義や特殊講義、史資料の取扱いや解読とその保存方法、文化財の調査や分析方法、地理学的調査研究方法など知識とリテラシー(DP①)にあたる学びをしっかりと身につけていきます。また、野外実習をはじめとするクロスバウンダリーな実践的探究活動を通じ、地域社会等と協働して問題を解決する実践力を身につけます(DP②2)。これらの学びを前提に卒業研究をおこない、その研究の過程では不断のリフレクションがなされます。以上の学修によりディプロマ・ポリシーで示される人材へと到達していきます。[日本研究・アジア研究コース]
日本研究・アジア研究コースは日本とアジアの文化・文学専攻と、日本語・日本語教育専攻から成ります。本コースでは、日本とアジアの文化・文学、および言語について複合的に学ぶことを通して、日本およびアジア諸国の魅力を理解するに留まらず、そこにあるさまざまな課題についても、文化的な側面から考え、行動できる力を身につけることを目標とします。
この目標に向けて、日本研究・アジア研究コースの各専攻では、まずは講義形式の授業やレベルに応じた語学授業において、それぞれの専門分野の基礎をしっかりと学びます(DP①)。同時に、より少人数での演習型授業における議論やグループワークを通して、日本を含むアジア諸国の現在、過去、そして未来について多面的に考える力を養うとともに国際感覚も磨いていきます(DP②、DP③)。そして最終的にはゼミでの学修と卒業研究等を通して、高い専門性を有するとともに、豊かな人間性と知性(文化性)、そして社会的責任をも備えた人材へと到達していきます(DP②、DP③)。[国際コミュニケーションコース]
国際共生コースは多様な専攻からなります。ディプロマ・ポリシーの狙い「国際的視点に基づく俯瞰的、総合的なビジョンの形成に資する人材育成」を、各専攻が各々の特長を活かして進めます。
英語国際コミュニケーション専攻では、ヨーロッパやアメリカの文化や文学を学び、その風土に暮らす人々の心情に触れ、理解する力を育みます(DP①)。実践的にはトランスランゲージングを活用し、複数の言語で自分の考えを表現する言語使用を学びます(DP②1)。外国語で意思が伝えられる自律した学修者をめざし、世界のどこの社会でも多様な他者と協働できる能力を身につけます(DP③)。
多文化共生専攻は、日本在住の外国人との豊かな共生社会を創造するために、多様性の理解と尊重する精神、国際的な知性と感性を磨きます(DP①、DP②1)。また多文化共生の現状と問題点を当事者へのアプローチを通して知り、実際に地域振興に貢献できる実践力と実行力を身につけます(DP②2、DP③2)。
国際関係学専攻では、世界の平和と持続性に関わる知識、すなわち国際情勢と国際問題について具体的に理解します(DP①2、DP②1、DP③2)。同時に、知識に基づく国際貢献で必要なコミュニケーション・スキルも身につけてもらいます。語学力はもとより、国際情勢・国際問題を世界レベルでのシステムの観点から説明できる力を養成します(DP①2、DP②2)。
これら複数分野から、核となるテーマを見つけ、そのテーマに沿った専門知識を修得します。同時に、コース内複数専攻でクロスオーバー学修に取り組み、テーマ学修に資する関連知識を身につけることで、学修成果を将来のキャリアに応用できる力を養成します。[スポーツマネジメントコース]
スポーツは個人の人格形成に留まらず、社会における思想、教育、文化、経済、心身の健康などに大きく影響を及ぼすものです。
トップアスリートをめざすための技能を高める演習・実技授業を核として(DP①)、スポーツと社会の関わりについて多角的に学修し行動することにより(DP②)、社会の先導者として多岐にわたる問題を解決できる能力と人格を形成します(DP③)。 - 通学課程全体のカリキュラム・ポリシーに示されたとおり、以上の学修の成果は、まず成績をもって評価されます。成績評価は、その基準がシラバスによって明示され、厳正かつ公正におこなわれます。また、成績と同時に外部アセスメントや定性的評価の手法をも加味して多角的に評価がなされ、可視化がおこなわれます。
- 本学の教育課程は、地元自治体や企業、他学の教員等から編成される外部評価委員の意見、また、学生からのアンケート調査の結果も踏まえて不断の点検と改革がおこなわれます。これにより、常に教育の質が保証されます。このことも通学課程全体のカリキュラム・ポリシーが示すとおりです。
アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)
近年は日本から海外に出ていく以上に、海外から多くの人たちが日本に来るようになりました。この人たちの多くは、もはや経済的な理由ではなく、日本の文化に興味・関心をもつ人たちです。国際日本学部ではこのような時代に対応できるような教育、研究を実施しています。すなわち、「日本を知り、世界を知る。世界を知り、日本をふり返る」のモットーのもと、「国際社会で通じる能力やグローバルな視点を持ち、地域社会や地域経済の発展に貢献する人材」の育成をめざしています。
国際日本学部では、以上の指針に基づき、さらに本学の建学の精神、目的、使命および教育方針に則って、以下の素養を備えた人材を積極的に受け入れます。
- 日本と世界、各国、各地域の多様な文化的事象(歴史、言語、文化、文学、国際関係など)に興味があり、常に知的好奇心、探究心、問題意識を持ち、問題解決能力と向上意欲のある者。
- 多角的な視点でものごとを見る力、多文化交流を通してさまざまな文化や考え方を受容する寛容な心と柔軟な思考力を持つ者。
- 国際的な視野を持ち、日本や世界が抱える諸問題の解決に寄与しようとする意欲のある者。
- 学んだ知識や技能を活かして地域社会や地域経済に貢献するため、積極的に地域産業やグローバル企業、地域行政に関わっていこうとする者。あるいは、自らの知識や技能を世界に発信しようとする者。
- 専門職(中学・高校の教師、博物館学芸員、図書館司書、日本語教員)の資格取得や大学院への進学を希望する者。
入学者の選抜においては、さまざまな試験をそれぞれの入試種別に応じて組み合わせ、上記の必要な素養を有しているかを評価します。
学力の3要素(「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」)を多面的・総合的に評価します。このうち「知識・技能」では、基礎的な教科の「国語」、「外国語」、「地理歴史」、「公民」、「数学」、「情報」などの基礎知識・技能を身につけていることが望まれます。また、「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」では、一定程度のコミュニケーション力や論理的思考力、行動力などを重視します。
建築&芸術学部 3つのポリシー
ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)
大手前大学建築&芸術学部は、所定の卒業要件を満たし、以下の目標に到達した学生に対して卒業を認定し、学士(学術)を授与します。
通学課程全体のディプロマ・ポリシーは、知識、実践力、信念と志を有し、社会に貢献できる価値ある人材を育成することを定めています。このことを基礎におき建築&芸術学部は、変化の時代をしなやかに生き抜くクリエイティブな人材を育成するというさらに具体的な学部固有の目標を置きます。
このような人材育成の目標から、建築&芸術学部を卒業するには、以下の要件が求められます。
- 専門分野で培った創造的な構想力と論理的な思考力を有していること。
- 互いの美の概念を尊重し、多様な人々と協働して問題を解決する能力を有していること。
- 表現と探究を通して自己を確立し、文化的で豊かな社会を構築する強い意志を有していること。
カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)
建築&芸術学部は、「専門に閉じない開かれた教育」を掲げます。
(1)さまざまな専攻に対して開かれた教育(2)地域に開いた教育(3)新しいものに対して開かれた意識を持つ学生の育成、これらを実践する教育課程を編成・実施します。
建築およびデザイン、造形芸術、メディア表現、舞台芸術などの創造活動と社会における文化創生を教育研究の対象とします。理論と実践による多様な学修活動をつうじて創造的な構想力と表現力、論理的な思考力を修得し、文化的に人間生活を考える素養を備えた感性豊かな人材を養成します。
本学部の授業は実技・実習を軸にして構成されています。各専攻分野においては、必要とされる知識と技能を修得するための基礎教育を重視します。学修を進めながら「つくること」「表現すること」「探求すること」をつうじて、ものづくりの本質に迫り表現の可能性を探ります(DP①)。専門教育プログラムは、専攻を横断したカリキュラムを編成して芸術・デザインに関する感性、幅広い知識、技術、柔軟な思考と自分の価値観を備えた人材を養成します。展覧会や公演による作品発表、コンペやインターンシップ、社会連携活動などの実践的な経験や多様な研究と実証(DP②)により、広範な文化芸術活動の社会的意義を理解し、自ら思考し表現へと昇華させる主体性の確立と創造的で豊かな人間性を涵養していきます(DP③)。
- 建築コース
建築コースは、建築とインテリアデザインのふたつの専攻を設けています。これらの専攻では、多くの授業において専門で必要とされる共通の知識や技能を学びますが、3年次以降においては、建物の設計や構造、環境などから建築を考える建築専攻と、住宅や店舗などの内部空間を考えるインテリアデザイン専攻について、それぞれの特有な分野に重きを置いた授業や研究を行います(DP①)。またどちらの専攻も授業における知識や技能の修得に限らず、インターンシップや地域活動などの実践的な経験を通して、建築・インテリアデザインと向かい合う姿勢の修得を図ります(DP②)。そして建築分野・インテリアデザイン分野の専門家として、暮らしやすく安全な社会の実現に貢献できる人材を育成します(DP③)。 - 芸術コース
芸術コースでは、専門教育プログラムは、デザイン造形美術、マンガ制作、映像・アニメーション、映画・演劇の4つの専攻を置き、作品制作などの創作活動を主体とする実技実習を軸にして構成されています。各専攻分野では必要な知識と技能を修得します(DP①)。また、共同制作や公演、展覧会、社会連携事業活動等、実践的な活動をつうじて、多様な人々と共同し、社会に発信をします(DP②)。そして、自ら思考し表現へと高めていける主体性の確立と創造的で豊かな人間性の醸成を図ります(DP③)。 - 以上の学修の成果は、まず成績をもって評価されます。成績評価は、その基準がシラバスによって明示され、厳正かつ公正におこなわれます。また、成績と同時に外部アセスメントや定性的評価の手法をも加味して多角的に評価がなされ、可視化がおこなわれます。
- 本学の教育課程は、地元自治体や企業、他学の教員等から編成される外部評価委員の意見、また、学生からのアンケート調査の結果も踏まえて不断の点検と改革がおこなわれます。これにより、常に教育の質が保証されます。
アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)
建築&芸術学部は、本学の建学の精神、目的、使命および教育方針に基づき、以下の資質を備えた人材を積極的に受け入れます。各種入学試験では、それまでに学習した教科の基礎的知識・技能および下記の資質を多面的・総合的に評価します。
- 創造的表現活動に対する関心・旺盛な探究心と自己を高めようとする強い意欲があること。
- 他者とコミュニケーションを取りながら協調・協働し、問題解決をしようとする意欲があること。
- 将来に対して明確な目標を持ち、自らの夢に向かって挑戦する意志があること。
ついては、学力の3要素(「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」)を多面的・総合的に評価します。このうち「知識・技能」では、基礎的な教科の「国語」、「外国語」、「地理歴史」、「数学」、「情報」、「芸術」などの基礎知識・技能を身につけていることが望まれます。また、「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」では、一定程度のコミュニケーション力や論理的思考力、行動力などを重視します。
入学者の選抜においては、さまざまな試験をそれぞれの入試種別に応じて組み合わせ、上記の必要な資質を有しているかを評価します。
現代社会学部 3つのポリシー
ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)
本学では、所定の卒業要件を満たし、学修によって修得した知識と能力をもって社会に貢献することのできる学生に学位を授与します。
通学課程全体のディプロマ・ポリシーでは、学位授与者が建学の精神である“STUDY FOR LIFE(生涯にわたる、人生のための学び)”を実現するのに必要な知識、実践力、信念と志を有していることを保証すると明記しています。このことを踏まえ、現代社会学部では、現代社会を多面的・学際的に捉えるための情報収集・分析能力、社会課題の発見・解決に資する実践力とよりよい社会の構築に向けた構想力・行動力、そして、社会の諸活動に主体的に参加する意志の育成に学部固有の目標を置きます。これらの能力が、変容を続ける現代社会に対応するために必要な力であるからです。この目標を踏まえ、現代社会学部では、以下の要件を満たす学生に対して卒業を認定し、学士(学術)を授与します。
- 豊かな教養、旺盛な自己開発精神、専門知識、そして自らの知見や技術を現代社会の実態把握や課題解決に活用するための能力を有していること。
- 現代社会で求められる優れた国際感覚と多様性理解を基礎として他者と協働し、社会課題を解決する実践力と、よりよい社会を構想し行動する力を有していること。
- 社会課題へ実践的に向き合う体験とその振り返り(リフレクション)を繰り返す学修によって育まれた豊かな人間性と、肯定的自己概念および社会的責任を果たそうとする強い意志を基盤として、社会の諸活動に主体的に参加する姿勢を有していること。
カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)
現代社会学部は、ディプロマ・ポリシーにおいて、現代社会を多面的・学際的に捉えるための情報収集・分析能力、社会課題の発見・解決に資する実践力とよりよい社会の構築に向けた構想力・行動力、社会の諸活動に主体的に参加する意志の育成を学部固有の目標として定めています。
本学部は、通学課程全体のカリキュラム・ポリシーに示された学部の専門教育を柱としつつ専門分野の垣根を越えたクロスオーバーの学びとともに、フィールドに出向いて実践的探究活動をおこなうクロスバウンダリーの学びを展開します。そしてその学びの経験を通じた振り返りを継続することを通じて、目標の達成をめざします。
- 1、2年次では専門的な学修・研究のための作法・技法(アカデミック・スキルズ)や情報機器の活用方法とともに、各専攻の入門科目を学んでいくことになります。これらの学びを通じて、多面的・学際的な視点から社会課題の解決に資する発想方法や技術を修得するとともに、より専門性の高い専攻科目の履修や将来の進路選択の準備を進めていきます。
-
本学部の各専攻のカリキュラムは以下の方針のもとに編成されます。
[メディア・社会学専攻]
メディア・社会学専攻では、社会学やメディア学に関連する専門知識や社会調査の技法を通じて社会の実態を捉える能力と、ビジネスや研究活動などの分野で情報メディアを効果的に活用する能力の育成をめざします。
この目標に向けて、本専攻では社会学やメディア学の概論的講義や専門授業、社会調査士資格科目に対応した授業を通じて、社会学・メディア学・社会調査法に関する知識とリテラシー(DP①)を身につけます。また、演習授業や学外での調査実習での活動を通じて、社会の多様な生活様式を捉える視野を育むとともに、社会課題の発見・解決に向けて他者と協働し社会を前に進めるための自己理解とコミュニケーションスキルを活かした実践力(DP②)を身につけます。さらに、これらの知識・リテラシーと実践力を活かしたゼミナールや卒業研究、演習授業などの活動を通じて、社会実践活動への積極的な参加につながる豊かな人間性、肯定的自己概念、社会的責任を果たす意識(DP③)を涵養します。[心理学専攻]
心理学専攻では、観察や実験などの科学的な方法によって、人間の行動や心のはたらき、仕組みを明らかにし、心を論理的に理解することをめざします。
その目標に向けて、心理学や心の測定方法に関する概論的講義や専門授業を通じて、専門分野の知識とリテラシー(DP①)を身につけます。また、実験や調査を伴う実習・演習での活動を通じて、他者への理解を深め協働して課題解決にあたる実践力(DP②)を身につけます。そのうえで、ゼミナール・卒業研究での卒業論文指導を通じて、心理学の知見と測定技術を社会で活用するための信念と志(DP③)を育みます。[地域価値創造専攻]
地域価値創造専攻では、経済学を基盤として、地域にある魅力や課題への気づきから豊かな地域づくりの実践に至るまで、主体的かつ実践的に行動できる人材の育成をめざします。
この目標に向けて本専攻では、現代社会を理解するための経済学を中心とする知識の体系の学習および、産官学民の連携活動から招聘する外部講師によるまちづくりに関する先端的な授業を通して、地域価値創造に必要な知識やリテラシーを身につけます(DP①)。またゼミナールをはじめとして、学内外の境界を越え、本物の社会に触れる授業を積極的に行うことで、社会実装を図るための行動力、実践力を養います(DP②)。これら知識・リテラシーの学修(DP①)と実社会での経験による学び(DP②)を行き来することで、地域への深い理解と社会的責任の意識を育むとともに、組織や社会における自らの居場所や役割を見出し、他者を尊重することができる豊かな人間性の醸成を図ります(DP③)。[観光マネジメント専攻]
観光マネジメント専攻では、現代の観光をめぐる社会環境やビジネスの専門知識を学ぶとともに、実践的な観光業のスキルを身につけることによって、持続可能な新しい旅の形を創造できる人材の育成をめざします。
この目標に向けて、資格取得に向けた科目や各分野の観光ビジネスに関する学び、および外部の実務家による専門授業を通して、広く観光に関する知識やリテラシーを身につけます(DP①)。また、演習授業やゼミナールでの活動では、学外での活動を積極的に取り入れることで、座学のみでは把握できない観光の実際を理解するとともに、観光サービス産業の課題を解決し、地域の観光の魅力を世界に向けて発信する力を養います(DP②)。これらの学修を通じて、観光資源となる地域の自然や歴史文化等への理解を深め、観光マネジメントに携わるために必要な“豊かな人間性”を育み、“社会的責任の意識”を高めます(DP③)。[情報・コンピュータ専攻]
情報・コンピュータ専攻では、現代社会の課題解決の手段として情報技術の活用を推進し、また、実践することのできる人材の育成をめざします。
そのために、プログラミングや人工知能(AI)、プロジェクト管理などに関連する概論的講義や専門授業を通じて、ITエンジニアやプログラマーの基礎となる知識とリテラシー(DP①)を身につけます。また、プログラミング実習や課題解決型の演習での活動を通じて他者と協働していく実践力(DP②)を磨きます。また、演習授業やゼミナール・卒業研究の活動を通じて、身につけた技術を社会実装する取り組みに参加させ、現代社会に貢献するための信念と志(DP③)を育てます。 - 通学課程全体のカリキュラム・ポリシーで示されているように、以上の学修の成果は、まず成績をもって評価されます。成績評価は、その基準がシラバスによって明示され、厳正かつ公正におこなわれます。また、成績と同時に外部アセスメントや定性的評価の手法をも加味して多角的に評価がなされ、可視化がおこなわれます。
- 同じく通学課程全体のカリキュラム・ポリシーで示されているように、本学の教育課程は、地元自治体や企業、他学の教員等から編成される外部評価委員の意見、また、学生からのアンケート調査の結果も踏まえて不断の点検と改革がおこなわれます。これにより、常に教育の質が保証されます。
アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)
現代社会は変容の激しい社会です。技術革新が進み、ヒト・モノ・カネ・情報がグローバルに移動する中で、私たちを取り巻く社会環境は変わり続け、新たな課題が日々生み出されています。現代社会学部では、このような「現代社会および、その社会を構成する個人のよりよい状態(ウェルビーイング)とは何か?」という問いを追求する教育・研究活動を実施しており、その活動を通じて、変容を続ける社会に対応する力を備えた人材の育成をめざしています。
現代社会学部は、上記の方針を踏まえ、本学の建学の精神、目的、使命および教育方針に共感し、現代社会のさまざまな事象や課題について自律的に考え、その課題解決および社会貢献をめざし多様な学問領域に挑戦する、以下の素養を備えた人を求めます。また、さまざまな適性と多様な背景を持った学生を国内外から幅広く受け入れます。
- 現代社会のさまざまな事象・課題に対する基礎的知識と問題関心を持ち、それらの教養・専門知識とその活用力を修得する強い意欲と向上心を有する人。
- 優れた国際感覚や多様性理解の素養と、他者とのコミュニケーションを積極的にとり課題解決を試みる意欲・行動力を有する人。
- 学修を通じて豊かな人間性と肯定的自己概念、社会的責任を果たそうとする意志を獲得する姿勢を有する人。
入学者の選抜においては、さまざまな試験をそれぞれの入試種別に応じて組み合わせ、上記の必要な素養を有しているかを評価します。
また、その素養の基礎となる学力の3要素(①知識・技能、②思考力・判断力・表現力等の能力、③主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度)を多面的・総合的に評価します。「①知識・技能」では、基礎的な教科である「国語」、「外国語」、「地理歴史」、「公民」、「数学」、「情報」などの基礎知識・技能を身につけていることが望まれます。また、「②思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」では、一定程度のコミュニケーション力や協調性、論理的思考力、行動力などを重視します。
経営学部 3つのポリシー
ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)
本学では、所定の卒業要件を満たし、学修によって修得した知識と能力をもって社会に貢献することのできる学生に学位を授与します。経営学部では、以下の要件を満たす学生に対して卒業を認定し、学士(経営学)を授与します。
- 社会の幸福と持続可能な発展に貢献するための高い志、広い視野、経営学の専門知識を備えている。
- 経営学の専門知識を用いて、社会における課題の解決策を考え、他者と協働してそれを成し遂げる力を備えている。
- 自らのキャリアを主体的に形成し、実践と内省を繰り返しながら成長する力を備えている。
カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)
経営学部は、国内外における経営現象を教育研究の対象とし、地域に軸足を置きつつ、企業や団体における課題解決を通じて、社会の幸福と持続可能な発展に貢献できる人材を養成するため、以下の方針に基づいて、教育課程を編成し実施します。
- 経営学に対する興味、関心につながる導入教育の充実
- 社会の発展に貢献する志と幅広い視野の涵養
- 幅広い経営学の基礎知識の修得
- デジタル社会に適応し得る知識の修得
- 実社会で活躍するための基礎スキルの修得
- 産学連携による理論と実践を結びつけた学び
- 自律的なキャリアの形成と他者の支援につながる学び
アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)
経営学部は、本学の建学の精神、目的、使命及び教育方針に基づき、以下の資質を備えた学生を積極的に受け入れます。
- 経営学を学ぶための基礎となる科目を幅広く履修している学力を保有する。
- 社会、組織、人について、深い洞察力をもって論理的に考え、表現できる。
- 社会的な問題の解決に関心を持ち、他者と協働できる。
- 経営学を中心とする本学の学びに興味を持ち、その学びを社会の発展に活かす意欲がある。
ついては、学力の3要素(「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」)を多面的・総合的に評価します。このうち「知識・技能」では、基礎的な教科の「国語」、「外国語」、「地理歴史」、「公民」、「数学」、「情報」、「商業」などの基礎知識・技能を身につけていることが望まれます。また、「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」では、一定程度のコミュニケーション力や論理的思考力、行動力などを重視します。
入学者の選抜においては、さまざまな試験をそれぞれの入試種別に応じて組み合わせ、上記の必要な資質を有しているかを評価します。
健康栄養学部 3つのポリシー
ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)
健康栄養学部は、教育方針に基づいて設定された授業科目を履修し、厳正な成績評価のもと基準となる単位数や成績評価基準を満たすことを学位授与の基準とします。学生は4年間の学びや課外実践、ボランティア活動をつうじて、社会に貢献できる健康と栄養の専門職としての能力・素養を備えることが求められます。卒業認定された学生には、学士(栄養学)を授与します。
健康栄養学部は、学位授与者が以下の知識・能力・態度を身につけていることを保証します。
- 実践的な管理栄養士として必要な素養を保持し、「食・栄養・健康・医療」に関する高度な専門的知識を身につけていること。
- 健康・栄養に関する課題を自ら発見し、多様な人々と協働して解決策を提案する能力を有していること。
- 栄養の専門家としての高い倫理観を持ち、社会的責任を認識し、それに基づいて行動できること。
カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)
健康栄養学部は、「食」をつうじて人々の健康および生活の質の向上を支援する栄養管理の専門家として、医療や福祉をはじめ、スポーツ、学校、企業など幅広い分野で社会に貢献できる人材を育成するため、以下の方針に基づいて教育課程を編成します。
全てのカリキュラムは、食と健康の専門家を育成することを目的とし、専門知識(Knowing)、困難を克服する問題解決能力(Doing)、豊かな人間性や高い倫理観などの社会人としての基盤的能力(Being)を養成する科目で構成されています。
- 総合科目
大学の学び方を身につける科目、外国語コミュニケーションや社会に出るために必要な情報活用方法を学ぶ科目、スポーツやキャリアアップに関する科目で構成(DP①、DP②2、DP③)。 -
専攻科目
(1)基礎導入分野
専門科目の学修の導入として位置付けられ、専門分野を学ぶために必要な基礎的な知識を学ぶ科目で構成(DP①1)。(2)専門基礎分野
専門分野における知識や技術を修得するための基盤となる分野として、「社会・環境と健康」(DP①1)、「人体の構造と機能および疾病の成り立ち」(DP①)、「食べ物と健康」(DP①)の3つの分野で構成。(3)専門分野
管理栄養士としての専門性を高めるために必要な分野として、「基礎栄養学」(DP①)、「応用栄養学」(DP①)、「栄養教育論」(DP①)、「臨床栄養学」(DP①)、「公衆栄養学」(DP①)、「給食経営管理論」(DP①)、「総合演習」(DP①2)、「臨地校外実習」(DP①2、DP②2、DP③)の8つの分野で構成。(4)発展分野
管理栄養士としての情報収集や分析および課題解決力を養うために、「卒業研究」(DP①、DP②2、DP③)など主体的に考える力を養う科目や、「ミライステッププログラム関連科目」(DP①、DP②2、DP③1)で構成。これらの教育課程は1年次から4年次まで段階的に配置し、講義・演習・実験・実習を組み合わせた授業を展開します。
- 通学課程全体のカリキュラム・ポリシーに示されたとおり、以上の学修の成果は、まず成績をもって評価されます。成績評価は、その基準がシラバスによって明示され、厳正かつ公正におこなわれます。また、成績と同時に外部アセスメントや定性的評価の手法をも加味して多角的に評価がなされ、可視化がおこなわれます。
- 本学の教育課程は、地元自治体や企業、他学の教員等から編成される外部評価委員の意見、また学生からのアンケート調査の内容をも踏まえて、不断の点検と改革がおこなわれます。これにより、常に教育の質が保証されます。このことも通学課程全体のカリキュラム・ポリシーが示すとおりです。
アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)
健康栄養学部は、本学の建学の精神、目的、使命、および教育方針に基づき、自ら課題を探求し、自律的に考え行動して解決の道を切り拓く意欲と能力に富み、食をつうじて国民の健康向上に貢献したい学生を受け入れます。
多様な能力を持った学生を幅広く受け入れるために、多様な選抜方法を用意し、公正かつ厳正な選考をおこないます。
健康栄養学部は、以下の素養を備えた人材を積極的に受け入れます。
- 管理栄養士をめざすための基盤となる知識・能力を有し、それらを発展させる意欲を持つ者。
- 健康と栄養の専門家として社会に貢献したいと考える者。
- 問題発見や解決にあたり、他者と積極的に協同作業をおこなう姿勢を持つ者。
ついては、学力の3要素(「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」)を多面的・総合的に評価します。このうち「知識・技能」では、基礎的な教科の「国語」、「外国語」、「生物」、「化学」、「数学」などの基礎知識・技能を身につけていることが望まれます。また、「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」では、一定程度のコミュニケーション力や論理的思考力、行動力などを重視します。
入学者の選抜においては、さまざまな試験をそれぞれの入試種別に応じて組み合わせ、上記の必要な素養を有しているかを評価します。
国際看護学部 3つのポリシー
ディプロマ・ポリシー(卒業認定・学位授与の方針)
国際看護学部は、学内での学びと国内外の広範な地域における学術交流活動を通して、グローバルな視野に立った教養を基礎とする知識および看護学の専門知識・技術・態度を修得し、国際化する社会において看護の専門家としての基盤的能力を修得した学生に対して卒業を認定し、学士(看護学)を授与します。所定の期間在学し、使命および教育方針に基づいて設定された授業科目を履修して厳正な成績評価のもと基準となる単位数、成績評価基準を満たすことを学位授与の条件とします。
本学は、学位授与者が以下の知識・能力・態度を身につけていることを保証します。
- 対象者が求める健康支援と看護を多職種と連携・協働しながら実践するための知識および技術を有している。
- 看護職者として課題を見出し、克服するために、主体的に課題に取り組むことができる。また看護問題・課題の解決に向けて、必要な論理的・実践的知識および資源を活用し、適切な看護方法を計画し安全かつ的確に行動することができる。
- 国際化する社会に暮らす人々に寄り添い、多様な人々の営みを理解、受容し、個人の価値観、信念、宗教観、生き方を尊重することができる等、グローバル人材としての資質を有している。
- 国際化する社会に貢献するグローバル人材として、臆することなく英語を主とする外国語でのコミュニケーションを図ることができ、かつ看護職者として医療現場において適切な医療英語を使った対応ができる。
- 各個人が有する多面的な価値観や伝統、および生活様式の多様性を受容する豊かな人間性と、人の健康と命に寄り添う高い倫理観と人権意識を持ち、看護の専門家として国際化する社会に貢献するという強い社会的責任感を有している。
カリキュラム・ポリシー(教育課程編成・実施の方針)
国際看護学部は、国際化する社会で暮らす多様な人々を対象に、人々の営みや価値観の違いを理解、受容する広い視野を持ち、対象者のニーズに応じた健康支援と看護を実践するグローバル人材としての看護師を養成するため、以下の方針に基づき教育課程を編成し実施します。
- 多様な人々の価値観や文化の違いを受容し行動するグローバル人材としての資質を養うため、日本人だけでなく、定住外国人や訪日外国人、帰国者、渡航者および在外日本人と、彼ら/彼女らを支援する人々の活動を理解するための科目を開講する。
- 国際化する社会の一員として、英語を中心に中国語や韓国語等の外国語を学ぶ。特に英語は1年次春学期から会話力や表現力を培うためネイティブスピーカーによる演習を実施するとともに、医療現場での対応を想定した医療英語を体系的に学び、臆することなく外国語でのコミュニケーションを図ることができる能力を身に付ける。
- 総合科目のうち基礎分野ではスポーツやセルフケアに関する知識を習得し、専攻科目の専門基礎分野において人のライフサイクルや相手を尊重し傾聴する姿勢を学ぶことで、多様な人々に寄り添った健康支援を行う看護師としてのコミュニケーション能力と対人スキルを高める。
- 看護に求められる多様な人と場を理解するため、阪神地区を基盤とした実習を1年次春学期から展開し、4年間を通して国内外での実習経験を積み重ねることで、対象者ひとりひとりに応じた健康支援の必要性を理解するとともに、看護の実践力を身に付ける。
- 専攻科目のうち専門基礎分野では、健康や疾病を理解する基礎医学関連科目を配置し、人体への科学的根拠に基づく理解を深めるとともに、看護職としての倫理観を身に付ける。
- 専攻科目のうち専門分野では、各領域に社会の国際化を反映した科目を配置し、海外での研究活動経験や医療現場での豊富な臨床経験を持つ看護師、助産師、保健師、医師等による最新の研究成果を取り入れた授業を行うことで、それぞれの領域を通したグローバルな視野と看護における課題を理解する。
- 実習では少人数グループを編成して教員と共に実習施設での看護の実践を行うと同時に、各人が対応したケースを全員で共有しながら振り返りを行うことで、複雑多岐にわたる医療現場のなかで多職種と連携して主体的・対話的に看護実践の応用力を発揮するための適切な看護の専門的知識と技術を身に付ける。
アドミッション・ポリシー(入学者受入れの方針)
国際看護学部は、本学の建学の精神、目的、使命および教育方針に共感し、自ら課題を探求し自律的に考え行動して解決の道を切り拓く意欲と能力に富み、多様性を有する対象者への看護を通じて国際化する社会に暮らす人々の健康支援とその向上に貢献するグローバル人材としての看護師を志す学生を受け入れます。
多様な能力を持った学生を幅広く受け入れるために、多種の選抜方式を用意し公正かつ厳正な選考を行います。
本学は以下の資質を備えた人材を積極的に受け入れます。
- 国際化する社会で暮らす人々への看護と健康支援に対する強い関心と旺盛な探究心および自己成長に対する意欲を有している。
- 看護職者が国際化する社会において果たす使命や役割について理解し、看護の専門家としてグローバルな社会に貢献しようとする熱意と意欲を有している。
- 多様性を理解、受容するグローバル人材としての看護師を目指すための基盤となる知識・能力を有している。
具体的には、学力の3要素(「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」)を多面的・総合的に評価します。このうち「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」では、本学で看護を学ぶ意欲と一定程度のコミュニケーション能力や論理的思考力、行動力等の資質を重視します。「知識・技能」では、多様な人々を理解、受容し適切なコミュニケーションをはかる基盤となる「国語」、「外国語」と、看護の基礎となる「生物」、「化学」、「数学」に関する基本的な知識・技能を有していることが望まれます。
入学者の選抜においては、さまざまな試験をそれぞれの入試種別に応じて組み合わせ、上記の必要な資質を有しているかを評価します。
