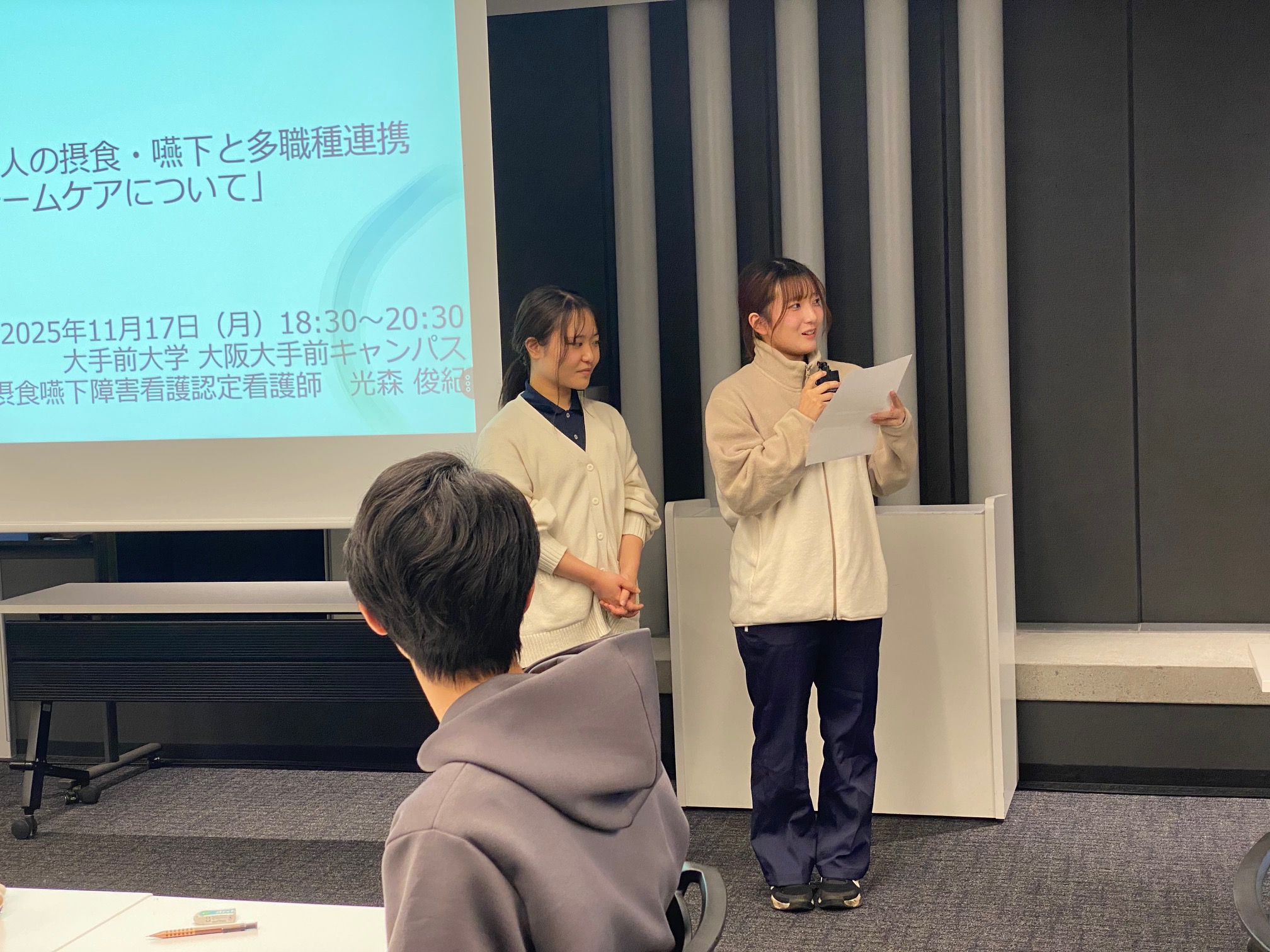ニュース・プレスリリース
【NSTクラブ活動】学内イベント『“食べる”を支える ~栄養×看護で学ぶ摂食嚥下~』を開催!
2025.11.20
- お知らせ
- 学生生活
- 健康栄養学部
- 国際看護学部
「“食べる”を支える ~栄養×看護で学ぶ摂食嚥下~」を2日間で開催
本学の課外活動団体「NST(栄養サポートチーム)クラブ」は、11月13日と17日の2日間にわたり、「“食べる”を支える ~栄養×看護で学ぶ摂食嚥下~」のテーマでイベントを開催しました。
管理栄養士・看護師それぞれの専門家を招いた今回の取り組みは、健康栄養学部・国際看護学部・短期大学歯科衛生学科が協働して実施する、本学ならではの実践的な学びの場となりました。
■ 11月13日 管理栄養士による講演・事例検討
初日は、介護老人福祉施設で活躍される管理栄養士であり、本学園卒業生の今和泉智哉氏を招き、介護施設における高齢者に特化した「摂食・嚥下」についての講演と、採血データや病歴・身体状況・必要栄養量・身体活動量などの情報をもとに、どのような食事・栄養摂取が最適であるかを考察する事例検討を実施いただきました。
参加学生は、講演・事例検討を通して、介護現場特有の摂食・嚥下の課題や、看護師・介護士・言語聴覚士との連携など、NSTの組織が整っていない環境での他職種への働きかけの重要性等について実践的に学ぶ機会となりました。



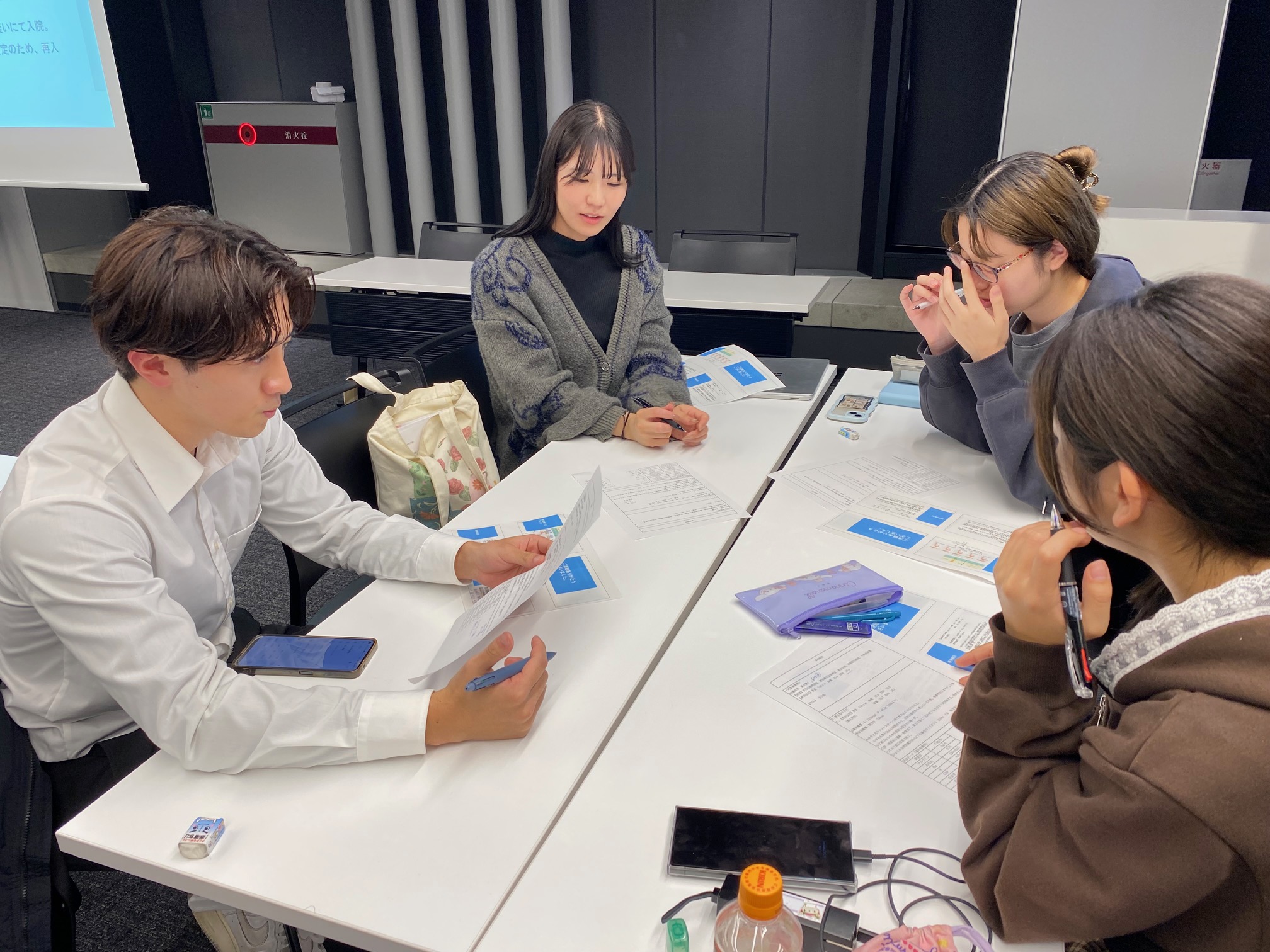
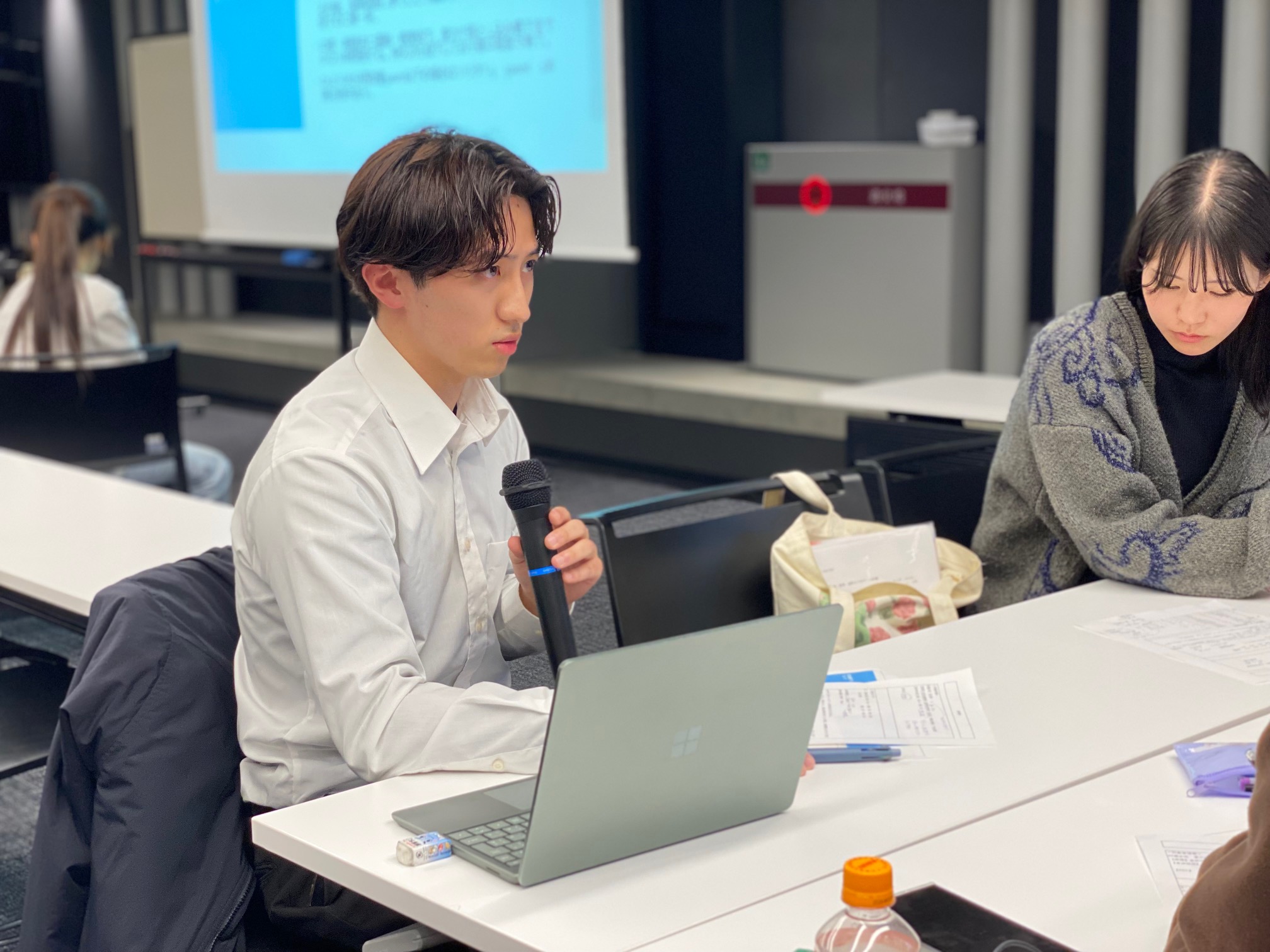

■ 11月17日 摂食嚥下障害看護認定看護師による講演・事例検討
2日目は、摂食嚥下障害看護認定看護師の光森俊紀氏による「病と共に生きる人の摂食・嚥下と多職種連携によるチームケア」についての講演および事例検討を実施。
摂食・嚥下のメカニズムを動画で確認したのち、3つの実践的な事例に取り組み、患者にとって“安全かつその人らしい食事”とは何かを多角的に考える学びを深めました。
特に、「栄養を摂ること」と「食事をすること」の違い、患者や家族の背景を踏まえる視点、口腔ケアにおいて歯科チーム介入が難しい場での看護師の役割など、将来の専門職として不可欠な視点を得られる貴重な機会となりました。
■ 参加者の声
国際看護学部2年の渡邉芽依さんは、「“栄養を摂ること”と“食事をすること”は同じではないこと。多職種連携では目的が同じでも職種ごとにアプローチやアセスメントが異なること。選択肢は一つではなく、異なる考えも間違いではないこと。また“患者さんの背景を知り、患者さん目線で考えること”が、個別性のある看護につながるということを学ぶことができました。」と語っていました。
NSTクラブ代表である健康栄養学部3年の藤原明音さんは、「管理栄養士と看護師の視点から“食べること”の重要性を学び、栄養摂取や摂食・嚥下に関する実践的知識を深めることができました。患者さんやご家族に寄り添う姿勢と多職種連携の大切さを実感し、“食べること”がエネルギー補給だけでなく、生活の楽しみでもあり、経口摂取がQOL向上や機能維持において重要であると再確認しました。将来は病院管理栄養士として、患者さんとていねいに向き合い、多職種と協働しながら患者さんの意思を尊重したケアに貢献したいです。」と2日間のイベントを振り返りました。
イベントに参加した国際看護学部の藤井ひろみ学部長は、「将来どの現場に進んでも、大学時代にNSTクラブで多職種の存在・役割について学んだ経験を活かして、チーム内に不足する専門職を補い、“自分にできること”を考え、動ける人になってほしい。」と参加学生にエールを送りました。
今回のイベントは、本学の3つの学部・学科が連携する希少な取り組みであり、学生が専門職としての視野を広げ、実践的に学ぶ貴重な機会となりました。NSTクラブは、これからも「多職種連携」に関する実践的な学びを深める活動を続けていきます。
(配信元:大阪大手前キャンパス 学生課)